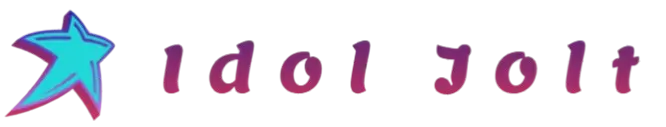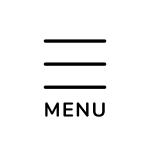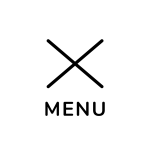蛭子能収さんの認知症、発覚から現在、そして未来への活動とは?蛭子能収さんの認知症公表とその後の生活
蛭子能収さんの認知症公表と、支える家族の姿に迫る。認知症と診断された蛭子さんの、仕事への情熱、ギャンブル愛、そしてマネージャーや妻との関係性を紐解く。夫婦の絆、介護の現実、そして認知症との向き合い方。笑いと希望に満ちた、心のこもったエッセイで、認知症介護のヒントも満載。

💡 蛭子能収さんの認知症発覚までの道のり、ご家族やマネージャーのサポート、そしてエッセイについて解説します。
💡 認知症公表後の蛭子さんの活動、仕事への情熱、そして周囲のサポート体制について掘り下げます。
💡 蛭子能収さんの認知症の症状、診断、そして家族との関係性の変化について焦点をあてます。
それでは、蛭子能収さんの認知症に対する道のりや現在の活動について、詳しく見ていきましょう。
認知症発覚までの道のり
蛭子能収さんの認知症公表、その裏にはどんな葛藤があった?
家族の闘病と葛藤
いよいよ、認知症発覚までの道のりについて迫ります。

✅ 蛭子能収さんが認知症であることを公表し、ご家族やマネージャーさんの協力を得て完成した「認知症エッセイ」が発売されます。
✅ 本書には、蛭子さんご自身の体験談に加え、妻・悠加さんの告白、認知症介護の先輩からのアドバイス、マネージャーや担当記者からのリポートなどが収録されています。
✅ 認知症の人と向き合う方法や介護する家族の心が楽になる考え方を提供するだけでなく、蛭子さん自身の「自分ファースト」な考え方から、介護のヒントを得られる内容となっています。
さらに読む ⇒エンタメラッシュ|芸能・エンタメ情報をいち早くキャッチ!エンタメ専門プレスリリース情報サイト出典/画像元: https://entamerush.jp/174246/蛭子さんの認知症発覚までの経緯を、ご家族やご自身の言葉を通して知ることができる、貴重な内容ですね。
2014年に軽度認知障害と診断された蛭子能収さんは、2020年7月に認知症と診断され、そのことを公表しました。
妻の悠加さんは、夫の認知症と闘う日々を綴ったエッセイ『認知症になった蛭子さん~介護する家族の心が「楽」になる本』で、認知症発覚までの道のりを詳しく紹介しています。
2017年に夫の異変に気付き、睡眠中の異常行動や記憶力低下の兆候に気づきながらも、認知症とは考えずに過ごしていたそうです。
しかし、夫の性格もあって認知症の可能性に気づくのが遅れたことを明かしています。
2020年に認知症公表に至るまでの葛藤や、介護する家族への心構え、そして夫婦の過去や現在の関係について語られています。
特に、結婚に至るまでの出会いのエピソードや、認知症発覚前に夫婦で経験した危機なども含め、読み応えのある内容となっています。
うーん、これは考えさせられる内容ですね。ご本人の性格もあって気づくのが遅れたってのが、リアルで他人事じゃない気がします。
認知症公表後の蛭子さんの活動
蛭子能収さんはどんな認知症で、どんな症状がありますか?
レビー小体型認知症です。
続いて、認知症公表後の蛭子さんの活動について見ていきましょう。
公開日:2021/04/15

✅ 蛭子能収さんは、アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症を併発している可能性が高いと診断された。
✅ 特にレビー小体型認知症の症状である幻視が強く、過去にはデパートの売り場で電車が走っているのが見えたなどの体験があった。
✅ 現在は定期的な通院により症状は落ち着いているものの、波があるため今後も注意が必要とのこと。
さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20210415/dde/012/040/014000c幻視の症状など、様々な症状がある中でも活動を続ける蛭子さんの姿は、本当にすごいですね。
蛭子能収さんは、認知症を公表しながらも活動を続け、「認知症になっても働き続けたい」と語っています。
蛭子さんは「レビー小体型」認知症で幻視やレム睡眠行動異常症などの症状が見られますが、競艇を見ているときはギャンブラーの表情に戻るなど、ギャンブルへの情熱は衰えていません。
認知症を公表するかどうかは事務所や家族と話し合い、本人の意欲を尊重しつつ、周囲への影響も考慮した結果、公表に至りました。
蛭子さんはテレビ出演よりも漫画を描くことを好みますが、ギャラが安いことからテレビ出演も続けています。
本記事では、蛭子さんの認知症と仕事、ギャンブルへの情熱、家族や事務所のサポートについて詳しく紹介しています。
ギャンブルへの情熱は衰えてないってとこ、なんか安心しました(笑)。でも、公表するにも色々な葛藤があったんですね。
次のページを読む ⇒
蛭子能収さんの認知症と、マネージャー森永さんの支え。公表の経緯、周囲の反応、夫婦関係の変化、そして介護の現実。温かい視点で綴る、認知症との向き合い方。